今回は、現代社会における表現手段におけるインターネットの問題について取り上げます。
私たち人間にとって他者への伝達・表現手段は大切なものです。表現手段の伝統的なものとして、新聞、ラジオ、テレビ、書籍、手紙があります。
ところが、最近では、インターネットが表現手段を提供する重要な社会的基盤(インフラ)となっています。その末端機器は、パソコンやスマートホンです。これら機器を通じて提供される、電子掲示板、ブログサービス、動画・画像共有サービス、SNS(X、Instgramなど)が表現手段・ツールとなりました。
では、インターネットの仕組みはどうなっているのでしょうか。
その仕組みは、コンテンツプロバイダー(ホスティングサービスプロバイダ、CP)とアクセスプロバイダー(経由プロバイダ、接続プロバイダー)(AP)によって、構成されています。
コンテンツプロバイダとは、電子掲示板管理者・ブログ系(サイト管理者)、プラットホーム管理者であり、具体的にいうと、Google、、Yahoo!知恵袋、SNS事業者、X(Twitter、Instagramなど)です。
アクセスプロバイダとは、インターネットへの接続を仲介するサービス業者のことで、具体的には、NTTコミューニケーションズのOCN、ソニーネットワークコミューニケーションズのnuroやドコモ、au、ソフトバンクといった携帯電話事業者のことです。
インターネットの利用者はアクセスプロバイダと利用契約を締結しなければならない。
この際の契約相手は、アクセスプロバイダです。例えば、パソコンの場合はNTTコミューニケーションズのOCN、スマートホンの場合はドコモと契約します。
この契約のさい、利用者は、その住所、氏名、電話番号、メールアドレスなど、利用者を特定される個人情報をアクセスプロバイダに知らせています。もちろん、利用料金の支払いに必要な情報(課金情報といいます)も知らせます。
インターネットでは利用者の個人情報が秘匿される仕組みになっています。
インターネットの利用者は、自分のパソコンやスマートホン等端末機器を操作して、①これらの画面に表示されている様々な情報を取得し(=情報の取得)、また、②自ら情報の発信者となり様々な情報を発信します(=情報の発信)。
これら情報の取得と情報の発信は、端末機器⇔アクセスプロバイダ⇔コンテンツプロバイダ⇔端末機器のルートを電子によって行き来します。このとき大切なことは、利用者の個人情報(住所や氏名等)はこの電子ルートには載っていないことがほとんどと言うことです。行き来するのは、1Pアドレス(Internet Protocol Addressの略で、インターネット網につながっている機器に割り振られた番号)です。
電子掲示板管理者・ブログ系(サイト管理者)、プラットホーム管理者である、Google、、Yahoo!知恵袋、SNS事業者、X(Twitter、Instagramなど)は、利用者の住所、氏名等は把握していません。だれが利用者であったか特定する個人情報は、1Pアドレスを辿り、アクセスプロバイダから利用契約の情報得を得るしかありません。
このように、インターネットの仕組みでは、情報の取得者や情報の発信者の個人情報はもともと極めて把握しにくい仕組み、秘匿される仕組みになっています。
ここに、インターネットによる表現手段の大きな問題点があるのです。
インターネットと通信の秘密及び表現の自由の保障
しかし、翻って考えると、インターネットによる表現手段は、その通信の秘密が基盤となっています。
憲法21条2項は、「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを犯してはならない。」と定めています。電気通信事業法 もその第3条で「電気通信事業者の取扱中にかかる通信は、検閲してはならない。」、その第4条1項で「電気通信事業者の取扱中にかかる通信の秘密は、犯してはならない。」、2項で「電気事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中にかかる通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後に措いても、同様とする。」と通信の秘密を規定しています。
インターネットによる表現手段は、その通信の秘密が基盤となっていることは、中華人民共和国国家情報法の第16条が「国家情報機関の職員は、関連する国家規則に基づき職務を遂行するにあたり、承認を得て対応する文書を提示した後、立ち入りが制限されている区域および場所に立ち入り、関係機関および個人~状況を知り、照会し、関連する国家規則に基づき、関連するファイル、情報および記事を照会し、または取り出すことができる。」と定めていることの対比でも明らかです。
また、匿名による表現の自由の保障も大切なことです。憲法21条1項は、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」と表現の自由を保障しています。この表現の自由には、匿名による表現の自由も含まれています。
この点、ヨーロッパ人権裁判所は、Satandard Verlagsgesellschaft Mbh v. Austria(No.3)判決(2021年)で、「当裁判所は、インターネットユーザーが身元を明かさないことへの関心も考慮している。匿名性は、長い間、報復を望まずして注目されることを開ける手段であった。その為、匿名性は、とりわけインターネット上において、意見、アイディア、情報の自由の流れを促進する手段となり得る。」と判示しています。
インターネットと通信の秘密及び表現の自由の保障が商業的利益を保障する基盤となっています。
この点は、明白です。
インターネット上の権利侵害の発生と深刻化、特にSNSによる誹謗中傷の深刻化。
一方、インターネット上では、違法な情報や有害な情報の流通が認められ、著作権を侵害する悪質な海賊版サイトの台頭や、SNS上での誹謗中傷などの深刻化など、様々な権利侵害に関する被害が発生しています(R2/12 「発信者情報開示の在り方に関する研究会 最終とりまとめ」の1頁)。
プロバイダー責任制限法の意義
そこで、通信の秘密・表現の自由と様々な権利侵害に関する被害の発生の調整のために、制定されたのがいわゆるプロバイダー責任制限法です。正式な名前は「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報開示に関する法律」といいます。2002(H14)/5/27に施行され、最近は、2021(R3)/4
の改正です。
その内容は大きくいって2つあります。
(1)第1は、プロバイダ(プロバイダにはコンテンツプロバイダとアクセスプロバイダの2つがあることは前述しました)の、権利が侵害された者(表現によって被害を受ける者)に対する責任の免責と、情報を発信する者からの責任追及に対する免責を定めた点にあります。
その内容の概要は以下のとおりです。
(権利を侵害された者に対する責任を免れさせること)
-誹謗中傷の表現手段のインターネットサービスを提供したとしてプロバイダに対し損害賠償を請求するケースを想定-
①プロバイダがインターネットによる情報の流通によってa他人の権利が侵害されていることを知っているときないしb他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるときに、②送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合には、損害賠償の責任を負う。しかし、それ以外は損害賠償の責任を免れる。
(情報発信者からの責任追及に対する責任を免責すること)
-プロバイダーが、発信する情報を違法として情報発信者に対するインターネットサービスの提供を制限したとき、情報発信者が発信を拒否されたとしてプロバイダに損害賠償を請求することを想定-
①プロバイダ情報の流通によってa他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当な理由があったとき、ないしb流通によって自己の権利を侵害されたとする者から、侵害情報及びその理由を示して、送信防止措置を講じるよう申出があった場合に、発信者に対して送信防止措置に同意するかどうか照会し、7日を経過しても同意しないとの申出がないときには、情報の送信を防止する措置を講じたとしも、情報の発信者に対して、損害賠償の責任を免れる。
(2)第2は、被害者がプロバイダに対して、情報発信者を特定する情報の開示請求ができることを定めていることです。
情報発信者を特定する情報の開示請求については次々回(次回のブログは法律以外の話題ですから。)に説明します。
これは、少し技術的になります。
名古屋弁護士 伊神喜弘
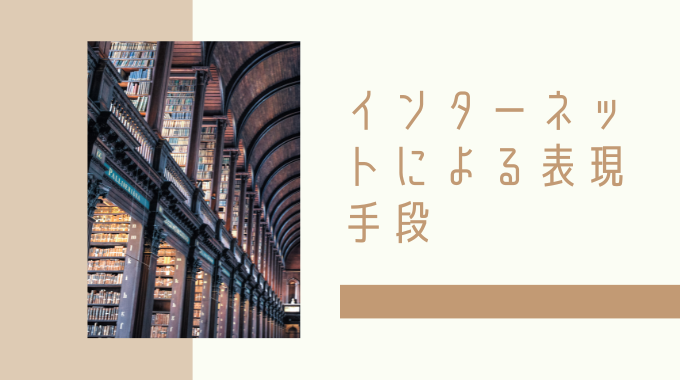


コメント