-取得時効の適用の問題点-
件は2012年10月に発生。韓国当局が仏像を回収し窃盗団を摘発。韓国政府が観音寺に仏像を返還しようとしたが、韓国の浮石寺が、そもそもその仏像は14世紀に日本人が主体の海賊である「倭寇」が、同寺から略奪したものであり、もともと同寺が所有権者だと主張して、韓国政府に対して、同寺に引き渡すよう裁判を提訴しました。第1審は、所有権を認めて、韓国政府に仏像を同寺に引き渡すように命じました。
○浮石寺に有利な証拠としては、14世紀に、「瑞山浮石寺」で地元民の願いを込めて作成されたとの記録が現存していたということです。第1審は同寺が仏像の所有権者と認めたものです。
○韓国政府が控訴したところ、第2審の裁判所は、仏像の所有権者は日本の観音寺だと認めて、浮石寺の引き渡しの請求を棄却しました。同寺は上告しましたが、2023年に韓国の最高裁判所も第2審の判決を認め、韓国政府が仏像を観音寺に引き渡すことになったというのです。
○結局、浮石寺も観音寺と話合い、観世音菩薩坐像の引渡に先立ち法要を営み、仏像の観音寺への返還を認めました。
中日新聞は、この仏像返還問題に関して、2025年5月22日(木)に、「津島の仏像返還」「日韓融和の象徴たれ」との社説を掲載し、そのなかで、「『倭寇』など歴史のかなたの出来事のようだが、箴言にも『他人の足を踏んだ者は忘れても、踏まれたほうは痛みを忘れない』ある。両国の友好を定着させる上でも、16世紀末の朝鮮出兵や、明治期の韓国併合以降の日本による植民地支配で、韓国の人々に苦痛を与えた過去を軽く見るようなことがあってはなるまい。」と指摘しています。
しかし、ここでは、韓国の裁判所が、観世音菩薩坐像の所有権者を、韓国の浮石寺ではなく、日本の観音寺だと認めた法的根拠について考えたいと思います。ただし、韓国の裁判所は、韓国の法律に基づいて判決していると思われます。したがって、私の説明は正確性を欠きますが、わたしは韓国の法律は不案内ですので、便宜、日本の民法に基づいて解説します(ただ、韓国の民法はその歴史的経過もあって、日本民法を引き継いだものですので、日本民法で考えてもいいと思います)。
仏像は不動産ではなく動産です。動産の場合には、民法192条は「取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意で有り、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。」と定めています。この条項は動産の即時取得の条項と言われています。倭寇による略奪であったとすれば、そもそも「取引行為」ではなく、この条項の適用はありません。
民法162条1項は、「20年間、所有の意思をもって、平穏に、且つ、公然と他人の者を占有した者は、その所有権を取得する。」と定め、2項は「10年間、所有の意思をもって、平穏に、且つ、公然と他人の者を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ,過失がなかったときは、その所有権を取得する。」と定めています。これらが、取得時効の条項と言われているもので、1項は長期取得時効、2項は短期取得時効と言われています。
これら取得時効の条項は、土地や建物等の不動産だけではなく動産にも適用される条項です。本件で問題となっている仏像も対象となります。
この条項で大切となるキーワードは「所有の意思をもって」です。従って、例えば、他人の土地や建物、動産を借りているときは、何年経過しても、取得時効が成立余地はありません。ただ、民法186条1項という条項があって、「占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有するものと推定する。」と定めていますので、一般には、占有者=取得時効を主張する者には「所有の意思をもって」が推定されます。しかし、この民法186条1項は、あくまで推定規定ですから、取得時効を争う者は、根拠を示せば、「所有の意思をもって」との推定を覆すことができます。本件即して考えると、韓国の浮石寺にといっては、「14世紀に、『瑞山浮石寺』で地元民の願いを込めて作成されたとの記録が現存していたというのですから、日本の観音寺が仏像を「所有の意思をもって」占有していた事実を覆すことができます
すると、何百年経過しようと、観音寺には取得時効は成立しないことになってしまいます。
では、第2審の裁判所は、いかなる理由で、日本の観音寺に「所有の意思をもって」占有してきたと認定したのでしょうか。この点、民法185条は「権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有させた者に対して所有の意思があることを表示し、または新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。」と定めています。この条項をそのまま形式的に適用すると、泥棒であっても、「これから俺はこの盗んだ物を俺のものとして占有する」と宣言すれば、以後その占有は泥棒が所有の意思をもって占有を始めたということができ、20年間経過すれば、時効で所有権を取得できるかという問題があります(10年の短期取得時効は、占有開始時点で過失のないことが要件とされていますので、盗人には、適用の余地はない。)。「盗人も自主占有者(=所有の意思に基づく占有者)である」という例が良く引かれます(我妻・有泉471頁)。20年間、盗品を占有しておれば盗人の所有になってしまうことになります。なにか正義の観念に反しますね。
この点は否定説が有力と言われており、不法占拠者に取得時効を認めた判例はみあたらないと言われています(藤原著 諸問題93-95頁)。すると、第2審は、倭寇が韓国の浮石寺から略奪した仏像について、一体、いかなる理由で、観音寺に所有の意思をもって仏像の占有を開始したと認定したのか問題となります。私は第2審の判決を見ていませんので解りません。考えられるのは、倭寇が仏像を転売し、複数の人間の間を転々として、その後、観音寺がその仏像を手に入れた(売買乃至寄付)というケースです。この場合、観音寺が手に入れた最後の段階だけを着目すると、売買乃至寄付ということになり、そこに所有の意思での占有開始と認定できないわけではないと思われます。ことによると、仏像がたまたま海から岸に流れついていたのを地元民が拾い、観音寺に持ち込んだということもあり得ます。
ここでは、観音寺の仏像の取得の縁起物語がどのようなものかここでは問題となります。おそらく、韓国の裁判所にこれらの資料も提出されていると思われます。
ここで、問題となったのは、仏像の所有権の帰属ですが、日本の北方領土とか、パレスティナでは、日本人とロシア人、パレスティナ人とユダヤ人とのあいだで、土地の帰属が争われることになります。勿論、現状では、戦争による勝者の土地の侵奪が実情であって、取得時効という問題は表面化しません。しかし、戦争ではなく、裁判所に土地の帰属を判断してもらうということになれば、今回の韓国の浮石寺と日本の観音寺との紛争は、平和的解決の道筋、一つの貴重な先例になると思います。そういう時代が速く来るといいと思っています。
名古屋弁護士 伊神喜弘
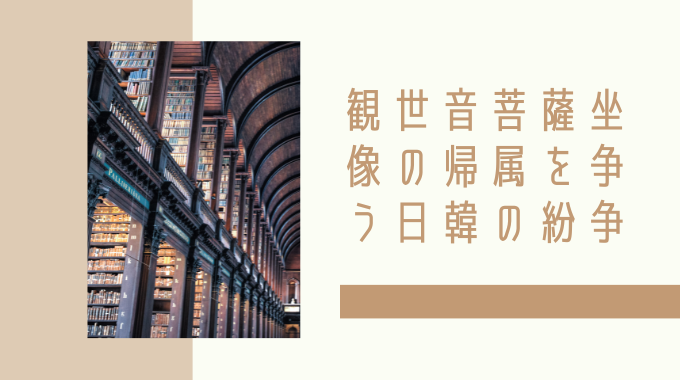
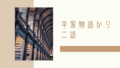

コメント