今年ある人から頂いた年賀状に、「反出生主義」という考え方について紹介がありました。紹介すると以下のとおりです。
「反出生主義」という考え方があることを、日経新聞の森岡正博氏(哲学者)のコラムで知りました。
「生まれてくるならば、その後の人生で痛みや苦しみを必ず経験する。生まれて来なければ、これらは一切経験せずに済む。だから人間は生まれてこないほうが良い。」
この考え方を提唱した南ア共和国の哲学者デヴィド・ベネター(1966~)は、「人類はなるべく早く滅亡した方が良い。」「子供を産むことは悪い人生をこの世に生み出し続けることになるから、それを避けなければならない。」という結論に達しています。
今回のブログでは、この考え方に対する私の考えを述べることにしました。
この反出生主義は、仏教の無余涅槃の考えに通じるところがあります。仏教では、生死流転を繰り返す生命体から離脱し、涅槃に達することを理想とします。涅槃とは古代インドの言葉でニルヴァーナといい、悩みのない永遠の平安の状態をいいます。涅槃に2つあり、まだ命がある間に涅槃を得るのを有余涅槃といい、死んで命がなくなってから涅槃を得るのを無余涅槃といいます。デヴィッド・ベネターは、①人類は滅亡した方がいい、②子供を産むことは避ける、ということです。すると、人類としての命を全面的に断絶・消滅させたほうがよいといっているのであって、無余涅槃に通じる思想と思われます。
もちろん、「生まれてくるならば、その後の人生で痛みや苦しみを必ず経験する」というのは真実です。しかし、だからといって、人類は早く滅亡した方がいいとか、子供は生まない方がいいというのは極端な考えと思います。この点、観音経では、「世尊、観世音菩薩は何の因縁を以てか観世音と名く。仏、無尽意菩薩に告げてのたまわく、善男子、若し無量百千万億の衆生有りて諸々の苦悩を受けんに、この観世音菩薩を聞きて、一心に称名せば、観世音菩薩その音声を感じて、皆解脱することを得せしめん。」といっております。
つまり、「無尽意菩薩がなぜ観世音菩薩はその名で呼ばれるのですか?と問うたところ、仏(釈迦)は答えた。多くの人々がさまざまな苦しみに悩んでいるとき、もし観世音菩薩の名を聞いて心を込めて唱えれば、観世音菩薩はその声を聞き、苦しみから救い出してくださる。」と観音経に書いてあるのです。
これは、デヴィッド・ベネターの反出生主義に対する反論・回答です。
しかも、観音経で観世音菩薩が救うことのできるいろいろな人間の苦難をあげていますが、その多くは、以下のとおり我々人間と人間の紛争です。
・或いは須弥の嶺にありて、人の為に推し堕されんにも、彼の観音の力を念ずれば、日の如くにして虚空に住せん(人に裏切られたとき)。
・或いは悪人に追われて、金剛山より堕ち堕ちんにも、彼の観音の力を念ずれば一毛を損ずること能わず(人から危害を受けたとき)。
・或いは王難の苦に遭い、刑に臨みて寿終らんと欲するも、彼の観音の力を念ずれば、刀尋いで段々に壊れん(権力から弾圧されたとき)。
・争い訟えられて官処を経、怖畏なる軍陣の中にも、彼の観音の力を念ずれば、衆の怨悉く退散せん(訴訟沙汰になったり、戦争で徴兵されたとき)
「生まれてくるならば、その後の人生で痛みや苦しみを必ず経験する」といいますが、これらは避けることが可能なものです。観音経は、「神通力を具足し、広く智方便を修して、十方諸々の国土、刹として身を現ぜずということなし。」といています。「広く智方便を修して」とは、智恵を絞って人間同士の紛争を解決することを意味しています。そのように努力していたら、観世音菩薩が不思議な力を出し、苦難がなくなるというのです。
子供を産むことは避けるという考えは、自然の摂理に反する点も大きな問題です。
人類は産むといういうことで連綿として続いてきました。そうであるのに、「生まれてくるならば、その後の人生で痛みや苦しみを必ず経験する。生まれて来なければ、これらは一切経験せずに済む。だから人間は生まれてこないほうが良い。」といってみても現実性がありません。
連綿として命が続くということを既定の事実として、どう生きるのか考えることが大切と思います。この点、デヴィド・ベネターの反出生主義は、物理的存在である身体という不存在が大切だという思想と思われます。心の方、魂といってもいいかもしれませんが、その救済について突き詰めて考えていないように思われます。物理的な身体と心ないし魂は一体物であって、物理的存在としての身体の滅亡ないし消滅(人類は早く滅亡した方がいい、人は早く死んだほうがいい)、発生防止(子供は産まない方がいい)を取り上げるだけでは不十分と思います。
この観点から、いろいろな宗教は、それぞれの考え(天国、最後の審判など)を提示していますが、仏教の無余涅槃はその一つです。
デヴィド・ベネターの反出生主義より、積極性があります。
最後に、羽渓了諦著 仏教の真髄(財団法人仏教伝道協会刊)の94,95頁から引用します。
原始仏教においてすでに涅槃を有余依と無余依との二種類に分けて、有余依涅槃は過去の業報として受けた肉体を持続しながら実現できる涅槃であり、無余涅槃は肉体を滅ぼして後にはじめて得られるものと規定したのである。これはたしかに厳粛な事故反省の必然的結果にあるに違いない。釈尊から自分と同じ覚証をえやという認可を与えてもらっても、その弟子たちは釈尊と自分たちとの間に利他的能力やその他の特性で格段の差があることを反省し、確認せざるを得なかったのである。しかも釈尊はいつも解脱者は「現未両世において安穏である。」と説き示されたのであるから、完全円満な涅槃の実現は肉体の滅後に期待されたのであろう。
この引用から分かることは、
①涅槃には二種類(有余依涅槃・無余依涅槃)がある。
②弟子たちは、自分が悟りを得たとしても、釈尊ほどの力はないと自己反省した。
③釈尊は「悟った者は現世でも来世でも安穏」と説いたが、完全な涅槃の実現は肉体の死後にあるとされた。
この考え方は、仏教における「解脱」と「生きることの苦しみ」の関係を理解する上で重要なポイントとなります。そして、デヴィッド・ベネターの反出生主義と比較すると、無余依涅槃の思想は、「苦しみながらも生き続けること」を前提としつつ、最終的な安らぎへと至る道を示す積極的な解釈であることが伝わるはずです。
名古屋弁護士 伊神喜弘
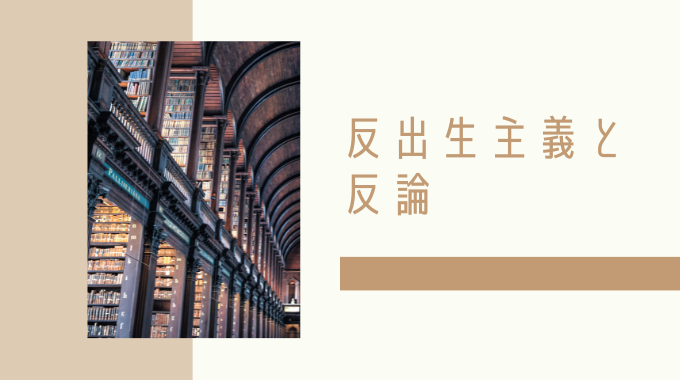


コメント