はじめに
最近の新聞報道などで、新潟県にある柏崎刈羽原子力発電所6、7号機の再稼働について報道されることが多くなっていますので、柏崎刈羽原子力発電所について基礎知識を提供したいと思いこのブログ記事を書くことにしました。
柏崎刈羽原子力発電所の概要
柏崎刈羽原子力発電所は1号機~7号機まであり、総発電量は821.2万キロワットで、1箇所の原子力発電の規模としては世界最大といわれています。
| 1号機 | 110万キロワット | 1985(S60)稼働 | 40年経過 |
| 2号機 | 110万キロワット | 1990(H2)稼働 | 35年経過 |
| 3号機 | 110万キロワット | 1993(H5)稼働 | 32年経過 |
| 4号機 | 110万キロワット | 1994(H6)稼働 | 31年経過 |
| 5号機 | 110万キロワット | 1990(H2)稼働 | 35年経過 |
| 6号機 | 135.6万キロワット | 1996(H8)稼働 | 29年経過 |
| 7号機 | 135.6万キロワット | 1997(H9)稼働 | 28年経過 |
ただし、2007(H19)/7/16に新潟県中越沖地震の襲われ、甚大な被害を被りました。
この地震の後、1号機、5号機、6号機、7号機は稼働を開始しました。
| 新潟県中越沖地震後に稼働 | 再稼働年月日 |
| 1号機 | 2010(H22)再稼働 |
| 5号機 | 2010(H22)再稼働 |
| 6号機 | 2009(H21)再稼働 |
| 7号機 | 2009(H21)再稼働 |
ところが、2011(H23)/3/11に東北太平洋震災・福島第1原発事故が発生し、新潟県中越沖地震の後再稼働していた、1号機、5号機、6号機、7号機も稼働を再度停止し、結局1号機~7号機の全部が稼働を停止し今日に至っています。
停止期間は、2号機、3号機、4号機は新潟県中越沖地震から今日〔2025(R7)〕まで約18年間、1号機、5号機、6号機、7号機は東北太平洋震災・福島第1原発事故から今日〔2025(R7)〕まで、約14年間となっています。
新潟県中越沖地震による柏崎刈羽原子力発電所の被災
ここでは、山口幸夫著 「柏崎刈羽原発の再開ありきを疑う」(原発と震災 岩波書店 20。21頁)を引用します。
「中越沖地震の揺れで稼働中の原発4基が止まった。それは2、3、4,7号炉で、2号炉は起動中だった。1、5、号炉は定期検査中で停止していた」「柏崎刈羽原発の耐震設計の地震想定は、地下250mの解放基盤面、設計用最強地震動(S1)300ガル、設計用限界地震動(S2)450ガルである。1号機の原子炉建屋底面では減衰して273ガルと想定されていた。しかし、そこでの観測値は680ガル(東西方向)で実に2.5倍である。観測された最大加速度は3号機のタービン建屋1階のタービをのせる台上で、水平方向2058ガルだった。そこでの限界地震動設計値は834ガルなので、約2.5倍である。」「全7機が設計用限界地震動の応答加速度値を超えたことは、重要機器に塑性変形が生じている可能性があるということ意味する。きずものの原発になったと見なすべきである。そして、原子炉内部の重要機器についてはいまだ調べることができず全くわかっていない。」
「中越沖地震の揺れで稼働中の原発4基が止まった。それは2、3、4,7号炉で、2号炉は起動中だった。1、5、号炉は定期検査中で停止していた」「柏崎刈羽原発の耐震設計の地震想定は、地下250mの解放基盤面、設計用最強地震動(S1)300ガル、設計用限界地震動(S2)450ガルである。1号機の原子炉建屋底面では減衰して273ガルと想定されていた。しかし、そこでの観測値は680ガル(東西方向)で実に2.5倍である。観測された最大加速度は3号機のタービン建屋1階のタービをのせる台上で、水平方向2058ガルだった。そこでの限界地震動設計値は834ガルなので、約2.5倍である。」「全7機が設計用限界地震動の応答加速度値を超えたことは、重要機器に塑性変形が生じている可能性があるということ意味する。きずものの原発になったと見なすべきである。そして、原子炉内部の重要機器についてはいまだ調べることができず全くわかっていない。」
難しいことが書いてありますが、当時の規制当局のが審査し、OKを出していた原子力発電所耐震設計設計技術指針・JEAG460F1970ないし原子力委員会 旧耐震設計審査指針が定める基準地震動を遙かに超える地震の揺れに襲われて大きなダメージを受けたのです。
1号機~5号機
これらの原子炉については、再稼働の動きは今のところありません。新潟県中越沖地震による重要機器へのダメージの解明が為されていないためと思われます。 ただし、かといって、廃炉するのかについても東京電力ははっきりさせておりません。
2024(R6)/8/22付の日経新聞の報道によると、6、7号機の再稼働後、2年以内に一部の炉を廃炉にする方針ということです。
6、7号機の再稼働の動き
東京電力そして政府が執念を燃やしているのが、6、7号機の再稼働です。
いずれも、2017(H29)/12/27に原子炉設置変更許可が許可され、その後、設計及び工事計画認可申請が認可されています。
これを受けて、東京電力は、今年〔2025(R7)〕の10月までに7号機を再稼働し、続いて6号機を再稼働しようとしています。
再稼働の不安ーその1(地震への不安)
もともと、柏崎刈羽原発は原子力発電所の立地として、適当ではなかったとの不安がぬぐえないといわれています。
この点について、山口幸夫著「柏崎刈羽原発の再開ありきを疑う」(原発と震災 岩波書店 19頁)は以下のとおり説明している。
柏崎刈羽地域は古くからの油田地帯であるが、1966年(昭和41年)6月、この地域に原発を誘致する話が自民党代議士の田中角栄と木川田東京電力社長の間に起きた。柏崎刈羽原発問題はここに始まる。田中はこの地の出身で、越山会王国を築き、後に総理大臣になった人である。その田中が関連する室町産業が、1966年(昭和41年)には、荒浜砂丘地のうち52町歩32筆の土地を買い占めた。この土地は1981年(昭和56年)、全部東京電力に買収された。
いったん用地が確保されてしまうと、漁業補償問題が片付けば、実質的に原発計画は進んでいく。その地域周辺の地震にたいして原発の建設が適切か否かを合理的に審査し、場合によっては、計画を変えるという余地がないんが日本の状況である。柏崎刈羽原発1号機建設に当たっては原子炉の炉心の位置がが二転三転した。
地質地盤が悪かったからである。越山会の地元ではあったが大きな反対運動が起こった。疑問を抱いた地元住民が地質地盤を調査し、『原発予定地盤は劣悪地盤ー公開された資料の分析と我々の結論』という謄写版刷りの資料(前16ページ)を発行したのは1974年(昭和49年)9月である。原発は設計変更をお迫られて、地下40mの半地下式原発となった。基盤の西山層は、建設当初は新第三紀・鮮新世前期の泥岩とされて板が、1980年(昭和45年)代の調査によって、年代はもっと新しいことが判明した。新第三紀から新第四紀にかけての堆積層だった。耐震設計審査の旧指針では、第三紀以前の岩盤に剛構造で設置するとされている。それに依拠するかぎり、柏崎刈羽原発は不適合ということになる(同上19頁)。
確かに、規制当局は阪神淡路震災→新潟県中越沖地震→東北太平洋震災のつど、基準地震動の見直しをして、同基準に基づく原発施設の補強をさせてきました。しかし、基準が見直されたとしても、その基準自体不十分と言われています。この点は、「震源を特定せず策定する地震動」について、特に際立っております。この点の説明は難しいので今回は説明を省略します。
再稼働の不安ーその2(使用済み核燃料への不安)
柏崎刈羽原発の使用済み燃料の保管状況〔2022(R4)〕は以下のとおりです。
| プラント | 保管量 | 管理容量 | 貯蔵率 |
| 1号機 | 1,835体 | 2,026体 | 約91% |
| 2号機 | 1,759体 | 2,475体 | 約71% |
| 3号機 | 1,733体 | 2,448体 | 約71% |
| 4号機 | 1,660体 | 2,445体 | 約68% |
| 5号機 | 1,934体 | 2,411体 | 約80% |
| 6号機 | 2,324体 | 2,538体 | 約92% |
| 7号機 | 2,489体 | 2,572体 | 約97% |
| 合 計 | 13,734体 | 16,915体 | 約81% |
使用済み核燃料を原子力発電所の敷地内に保管することは極めて危険なことです。その危険性は福島第1原発事故で日本国民は目の当たりにしました。もともと,政府の方針では、使用済み核燃料は再処理されてプルトニウムを回収したうえ、地中深く埋めて処分する計画ですが、一向その計画はすすんでおらず、原発を稼働させればするほど全国の原子力発電所に使用済み核燃料が増加するばかりです。
2024(R6)/9/25付日経新聞は、柏崎刈羽原発から青森県むつ市の使用済み核燃料の中間貯蔵施設に69体搬出したとの報道がされていますが、取り繕いです。
2025(R7)/1/9付日経新聞は、「スエーデン エネルギー起業・産業相 エッバ・ブッシュ氏」の「核のごみ解決急務」として、「ただ、日本はスエーデンと異なり「核のごみ」と呼ばれる使用済み核燃料を地下深く埋める地層処分の場所が決まっていない。行き場がなくたまり続けるのは安全保障上も問題が大きい。原発建設と最終処分はセットで考えなけらばならない。さらに、日本は世界有数の地震・火山大国だ。周辺の住民らが安全且つ確実に非難できるインフラや支援の仕組みを国の責任で整備する必要がある。」との見解を報道している。
名古屋弁護士 伊神喜弘
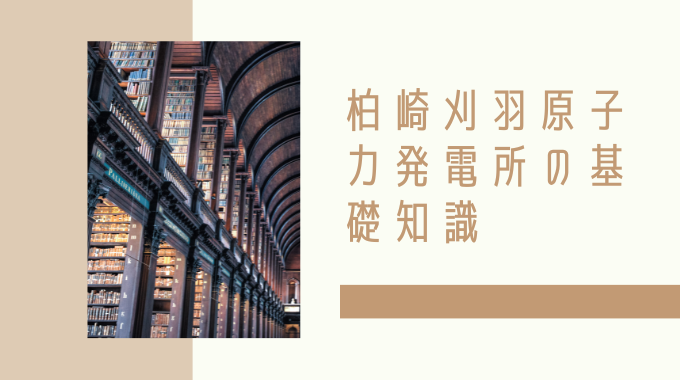

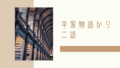
コメント