平家物語から二話
今回は父親と息子との交情について平家物語から2話を御紹介します。この二つの話は、どちらも「父と息子の交情」を描きながら、まったく異なる人間像を浮かび上がらせているとことに興味深さがあります。
それでは見ていきましょう。
第一話 平家物語 巻八 「妹尾最後」
平家が源氏に追われて、寿永2年(西暦1183年)2月に都落ちしてから壇ノ浦で敗れ平家が滅亡するまでの2年間は、主に瀬戸内海やその沿岸地域で数多くの戦がありました。
源氏側の武士も平家側の武士も、父と息子が共に戦う場面が数多く出てきます。
平家の武士妹尾兼康とその息子妹尾宗康の話です。2人は備中板倉川の戦で源氏に敗れ逃亡します。そのさい父は敵の馬を奪いとって逃げますが、息子は徒歩で逃げます。要領が悪かったのでしょう。息子は馬に乗っていないうえに、もともと肥満というハンディキャップがあり、ついていけません。甲冑を脱ぎ捨てましたが1町も逃げると歩くことさえできなくなりました。そして父との距離も9町余も離れてしまいます。
そこで父兼康は歩けなくなってしまった息子小太郎のところに戻ります。
源氏の追手が迫ってきている状況ですから、とって返すことは息子とともに戦死することを意味しています。
戻ってきた父をみて息子は「私は力量のない者です。父上に追いついて行けなくなった時点で自害すべきでしたのにしませんでした。こうして父上が私のことを心配して戻られたということは御自分の命を失うことを覚悟されてのことです。父を殺してはいけないという仏様の教えに背くことになります。」と自分を捨ておいて逃げてくれるよう頼みます。しかし、父は「私も覚悟を決めてお前のところに戻ってきたから、敵から逃げることなどしない。安心しなさい。」と言葉を返します。
そこに源氏の追手50騎が迫ってきました。万事休すです。父は息子の首をはね、自らは追手の源氏50騎の中に突っ込み死力を尽して闘い討死しました。
全て覚悟した行為でした。
第二話 平家物語 巻九 「敦盛最後」
平家一族は文治元年(西暦1185年)3月、下関海峡の壇ノ浦に追い詰められ、亡き清盛の妻に抱かれた8歳の幼帝・安徳の入水とあい前後して、あるいは戦死し、一門の主力はことごとく、海に消えました。清盛の後継者である太政大臣宗盛とその子清宗は海に入りましたが、宗盛は海から引き上げられ源氏の捕虜となっています。
平家一門の主要メンバーは次々と入水するため海に身を投げていきます。しかし、宗盛と清宗はなかなか入水しようとしません。
平家一門はみなこのように入水して死んでいった。しかし、宗盛、清宗親子は一向、入水しようとせず、船の端に立ちすくんで四方を見ていた。家来の侍は余りにも情けないので、まず宗盛の傍を通るふりをして海に入水させた。
清宗が父が入水したのを見て自分も入水した。外の人々は入水するとき重い鎧をきてそのうえ重量のある物を抱いて、入水したら決して2度と海の上に浮かび上がらないようにしていたが、この父子はそんなことはしておらず、その上泳ぐのが2人とも上手であったので、入水しても海に沈まなかった。
そして、父の宗盛は子どもの清宗が沈めば、自分も沈もう、助かるのであれば自分も助かりたと思っている。子どもの清宗も父が沈めば自分も沈もう、助かるのであれば自分も助かろうと思い、父と子はお互いに海に浮かんで目を見交わしていた。そんなことをしているとき、源氏の伊勢三郎義盛が、小舟をつっとよせて、熊手でまず清宗を引き上げ、次に宗盛を引きあげた。
対照的な平家物語の2話
父親と息子との交情について二話取り上げましたがこの二つの話は、どちらも「父と息子の交情」を描きながら、まったく異なる人間像を浮かび上がらせています。
妹尾兼康と小太郎の話は、武士道の理想的な一例です。父は息子の命を最後まで背負い、自らの死をもってその責任を果たします。たとえ勝ち目がなくとも、「親として、武士としてどうあるべきか」を貫いた姿は、時代を超えて胸を打ちます。血縁を超えた覚悟と愛情の形がそこにあります。
一方で、宗盛と清宗の話は、武士というより「人間」の弱さや本音が浮き彫りになります。「死にたくない」という本能と、「父が沈めば自分も」「子が沈めば自分も」という互いの依存は、滑稽さすら伴います。ここには覚悟も潔さも乏しく、むしろ「生きたい」という執着と、父子の情に揺れる様が見て取れます。まさに理想と現実、英雄譚と人間劇との対比です。
この両者を通じて感じるのは、「親子の情」にもいくつもの形があるということです。美しく散る父もいれば、共に沈み損ねて生き延びる父子もいる。どちらも真実の一端であり、時代の価値観と人間の心の間で揺れる姿を『平家物語』は見事に描き分けています。
まとめ
この二話の対比は、武士の理想と人間の現実、その両方を浮き彫りにし、父と子という普遍のテーマに深い陰影を与えています。親子の愛情と忠義の狭間で揺れる姿は、現代の私たちにとっても多くの示唆を与えてくれます。清く死ぬことが美徳とされた時代においても、なお生きたいと願う心は消えなかった。そのことが、かえって「生きるとは何か」「愛するとは何か」を考えさせるのです。
名古屋弁護士 伊神喜弘
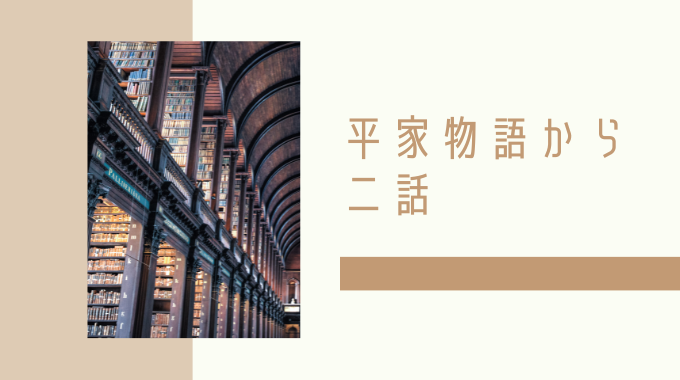
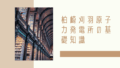
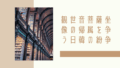
コメント