この記事では『金剛般若経』の核心──つまり「何ものにも執着せずに、人のために尽くす」という教えを、現代の生き方に結びつけて説明していきたいと思っています。
1、金剛般若経の冒頭は次のように始まります。
かくの如くわれ聞けり。ある時、仏、舎衛国の祇樹給孤独園に在して、大比丘衆1250人とともなり・その時に世尊は、食事に衣を著け、鉢を持して、舎衛大城に入りて食を乞い、その城中において次第に乞い終わって、本処に還り、飯を食し終わって、衣鉢を収め、足を洗い終わり、座を敷きて坐したまいき。時に長老須菩提は、大衆の中に在り、すなわち、起ちて、偏えに右の肩を袒ぎ、右の膝を地に著け、合掌恭敬して、仏の申して言う。
「希有なり、世尊よ、如来はよくもろもろの菩薩を護念し、よくもろもろの菩薩に付嘱したもう。世尊よ、善男子善女人、アノクタラサンミャクサン菩提の心を発さんに、まさにいかんが住すべき、いかんがその心を降伏すべきや」と。仏言いたもう、「よいかな、よいかな、須菩提よ、汝の説く所の如く、如来はよくもろもろの菩薩を護念し、よくもろもろの菩薩に付嘱す。汝、今、あきらかに聴け、まさに汝のために説くべし。善男子善女人、アノクタラサンミャクサン菩提の心を発さんに、まさにかくの如く住し、かくの如くその心を降伏すべし。」「唯、然り、世尊よ、願わくは聴かんと欲す。」
仏、須菩提に告げたもう、「もろもろの菩薩・魔訶薩は、まさにかくの如くその心を降伏すべし。
『あらゆる一切衆生の類、もしは卵生、もしは胎生、もしは湿生、化生、もしは有色、もしは無色、もしは有想、もしは無想、もしは非有想、もしは非無想なるもの、われ、皆、無余涅槃に入れて、これを滅度せしむ。かくの如く無量無数無辺の衆生を滅度せしめたたれども、実には衆生の滅度を得る者無し』と。何をもっての故に、。須菩提よ、もし菩薩に、我相・人相・衆生相・寿者相あらば、すなわち、菩薩にあらざればなり。
また次に、須菩提よ、菩薩は法においてまさに住する所無くして布施を行ずべし。いわゆる、色に住せずして布施し、声・香・味・触・法に住せずして布施するなり。須菩提よ、菩薩はまさにかくの如く布施して相に住せざるべし。何をもっての故に。もし菩薩、相に住せずして布施せば、その福徳は思量すべからざればなり。
【現代語訳】
あるとき、お釈迦様は舎衛国(しゃえこく)の祇樹給孤独園(ぎじゅぎっこどくおん)という場所にいて、1,250人の大勢の弟子たち(比丘=修行僧)と一緒におられました。そのとき、お釈迦様は食事の時間になると衣を身につけ、食器である鉢を手に持ち、舎衛国の都(舎衛大城)に入って、家々を順に回って托鉢(たくはつ=食べ物を乞う修行)をされました。町の中で托鉢を終えると、もとの場所に戻り、いただいた食事をとり終え、衣と鉢を片づけ、足を洗い、座に着いて静かに坐られました。そのとき、長老の須菩提(すぼだい)は大勢の弟子の中にいて、立ち上がり、右肩を出して衣を整え、右ひざを地につけ、両手を合わせて恭しくお釈迦様に申し上げました。
須菩提は言いました。「本当にめずらしく尊いことです、世尊(お釈迦様)。如来(にょらい=真理を悟った方)は、すべての菩薩(ぼさつ=悟りを求めて修行する人)をよく守り、導き、そして教えを託しておられます。世尊よ、もしも善い男や善い女が“最高の悟り(アノクタラ・サンミャク・サンボダイ)”の心を起こそうとするなら、どのようにその心を保ち、どのようにしてその心を静め、迷いを鎮めればよいのでしょうか?」
するとお釈迦様は答えました。「よい質問だ、よい質問だ、須菩提よ。あなたの言うとおり、如来は菩薩たちをよく守り、導き、そして教えを託している。それでは今、よく聞きなさい。私はこれから、あなたのために説こう。もしも善い男や善い女が“最高の悟り”の心を起こすなら、このように心を保ち、このように心の迷いを鎮めるべきである。」
須菩提は言いました。「はい、世尊。ぜひお聞きしたいと思います。」
お釈迦様は須菩提に言いました。「菩薩(悟りを求める者)は、次のようにして心をおさめ、迷いを鎮めるべきである。──すべての生きとし生けるものを、私は完全なる悟り(涅槃)へと導こう。卵から生まれるもの、胎内から生まれるもの、水の中から生まれるもの、または、心の力で変化して生まれるもの(化生)。形のあるものも、形のないものも、意識のあるものも、意識のないものも、意識があるともないともいえないものも──あらゆる無限の命あるものすべてを、私は悟りへと導き、救い尽くそう。だが、たとえ無量無数の生きものを救ったとしても、“実際に救われた生きものがいる”とは思ってはならない。なぜなら、須菩提よ、もし菩薩の心の中に “私” とか “人” とか “生きもの” とか “寿命ある者” というような区別や執着があるなら、その人はほんとうの菩薩ではないからである。さらに言おう、須菩提よ。菩薩は、何ものにもとらわれない心で「布施(ふせ=施し)」をしなければならない。つまり、色(姿・形)にとらわれずに施しをし、音や香り、味や触れる感覚、あるいは心の働き(法)など、どんな対象にも執着せずに施しを行うのだ。須菩提よ、菩薩はこのように“相(すがた)”にとらわれない施しをしなければならない。なぜなら──もし菩薩が、何ものにも執着せずに施しをすれば、その人が得る功徳は、計り知れないほど大きいからである。」
2、誰でも、自分の利益だけでなく人のためになりたいと思って生きていること
おそらく誰でも、自分の利益だけでなく、人のため世の中のためになりたいと思って生きていると思います。これが、お経にいうアノクタラサンミャクサン菩提をめざすために心を降伏することを指しています。 アノクタラサンミャクサン菩提とは立派な人生を送りたいという希望・心持ちを指しており、降伏とはそのために毎日、毎日忘れないようにして保つべき心構えのことをいっていると思います。
人のため、世の中のためになる行為にはいろいろな行為があります。例えば、お金を渡す・寄付するとか、働く場所を提供する・仕事斡旋するとか、病気を治す、人が争いごとで苦しんでいるとき良い解決をすることとかいろいろなことがあります。その中でも最も人のため世の中のためになることは、人々に心の安心を与えることが一番だと思います。そして、人が安心を得ることの中でも、最も大きいことは、死後の安寧を得ることです(こういうことは若いうちはなかなか分かりませんが、年を重ねると分かってきます。)。したがって、人のためになる究極的な行為は、人に死後の安寧をあたえることです。お釈迦様は、人のため、世の中のためになろうと決意するならば、それは何かというと、人々に、いや、生きとし生けるものに対して、その死後乃至消滅後の安寧を与えるようにすることだというのです。
無余涅槃というのは、体もなくなって心の永遠の安寧を得ることをいいます。我々人間でいうと、体も無くなるというのは死後のことを指していますので、死んで後、心の永遠の安寧を得ることをいっています。『あらゆる一切衆生の類、もしは卵生、もしは胎生、もしは湿生、化生、もしは有色、もしは無色、もしは有想、もしは無想、もしは非有想、もしは非無想なるもの、われ、皆、無余涅槃に入れて、これを滅度せしむ。」とうのは、人間だけでなく、一切の生きとし生けるもの(卵生とは、鳥類、爬虫類、両生類、魚等、胎生とは哺乳類、湿生とは蚊・蛇のように湿気に依って生じるもの、化生とは托することなく忽然と生まれたもの、神々(諸天)や宇宙の最初の人など、有色とは色身を有するもの、欲界と色界との有情をいう、無色とは色身を有しないもの、有想とは思想を有する状態、無想とは仏教以外の教えが最高の悟りとするところ、非有想とは思想を有する状態でないもの、非無想とは仏教以外の教えが最高の悟りとするものでないもの)についても、その死後若しくは消滅後に永遠の安寧を得ることをいいます。したがって、お釈迦さんは、最も世の中のためになることは、一切の生きとし生けるものが、その死後あるいは消滅後に心の永遠の安寧を得るようにすることだといっているのです。
3、なぜ、お経では続いて我相・人相・衆生相・寿者相のことをいうのか
しかし、お経は続いて、「『・・・かくの如く無量無数無辺の衆生を滅度せしめたたれども、実には衆生の滅度を得る者無し』と。 何をもっての故に、。須菩提よ、もし菩薩に、我相・人相・衆生相・寿者相あらば、すなわち、菩薩にあらざればなり。」という。我相とは自我のこと、人相とは個体という思い、衆生相とは生きているものという思い、寿者相とは個人という思い、をいう。これらは、霊魂または人格主体を意味するものとして、仏教の内外で考えられていた概念であるといことだそうです。これらは一言でいえば、自我、他者の中に生きながら他者と区別してオレガ、オレガということを思う自分を大切にすることである。お経は、生きとし行けるものに対して無余涅槃を与えて救うという行為は、ことはこのような自我意識に基づく行為に出たものだというのです。そして、生きとし行けるものに対して無余涅槃という最高の贈り物をしたとしてもそれが自我意識に基づくものであるから、よく考えると、他者は救われていないといっているのです。
そして、その一方、人のため、世の中のためにと救済行為に努力してきた、当の自分自身も菩薩とはいえないといっています。なぜならば、自我意識に基づく他者を救う行為をしたとしてもその人は結局この世の中で人とのつながりを持ち他者の中で生きていながら、そして、他者とのつながりのないかぎり生きていけないのに、自己を他者とことさらに区別・区分しオレガ、オレガという自我意識にとらわれて人のため、世の中のためになることをしてきたからなのだと言っています。だから、アノクタラサンミャクサン菩提をめざすために心を降伏して生きる菩薩とはいえないというのです。
4、では、一体どういう心持ちで生活したらいいのか
では、どうしたらいいのか。「また次に、須菩提よ、菩薩は法においてまさに住する所無くして布施を行ずべし。いわゆる、色に住せずして布施し、声・香・味・触・法に住せずして布施するなり。須菩提よ、菩薩はまさにかくの如く布施して相に住せざるべし。何をもっての故に。もし菩薩、相に住せずして布施せば、その福徳は思量すべからざればなり。」
布施しなければならないことは、他者が無余涅槃を得るようにすることですが、この布施は布施をしたということが形に現れてはならない。布施したときそれが形として現れたときは、それがとりもなおさず自我意識によるものであり、人のため、世の中のためという初心を台無しにしてしまうからです。
したがって、人のため、世の中のためにするという行為をするにしても風のように形に残らないようにしなければならないわけです。
しかし、このようにして、生きていくことは大変難しいことです。
5、ある人の回答
ある人がじーと話を聞いた後に、ぽつりと、「難しいことをいうのですね。」「そんなこと、難しくないよ。」「正当な対価で他人にサービスを提供すればいい。」「それだけのことだ。」と言いました。
無償で人の為に尽くすのではなく、他人が喜ぶことをしてお金を貰うことが肝腎ということです。突き詰めればそれだけのことでした。
名古屋弁護士 伊神喜弘
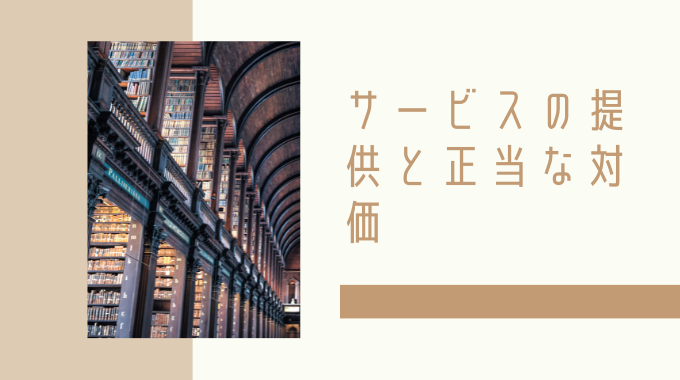
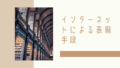
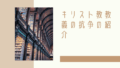
コメント